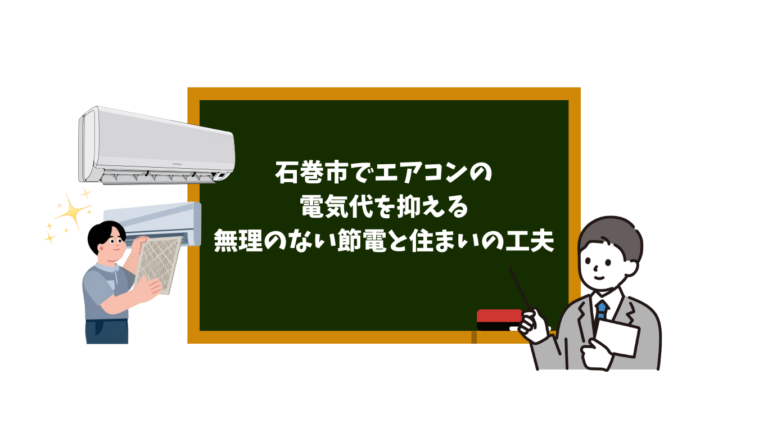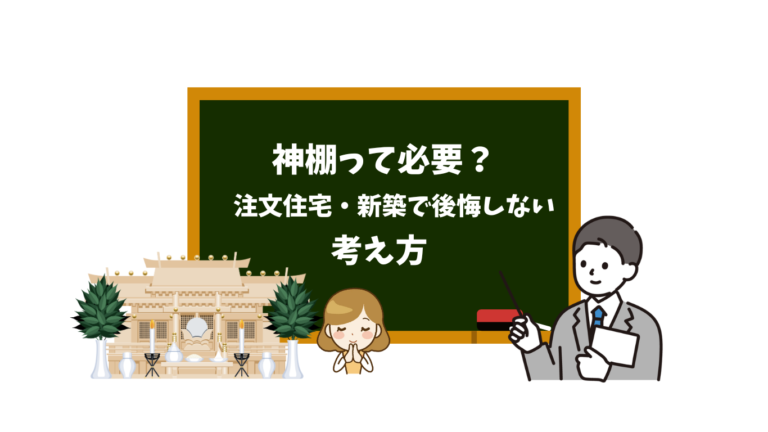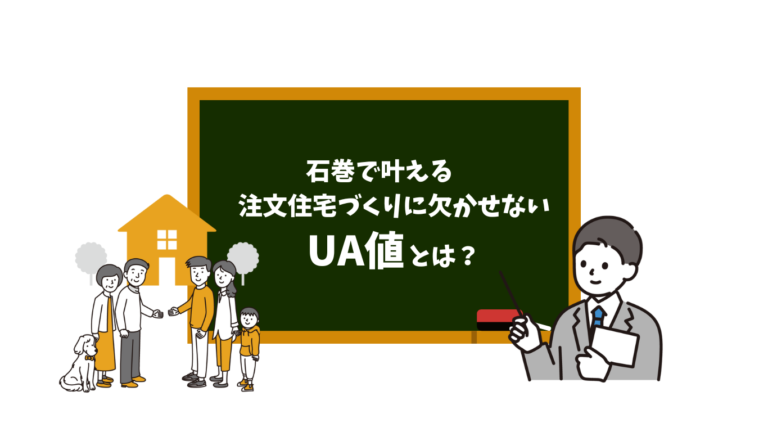住まいは、家族構成やライフステージの変化に伴って、その暮らし方も変化していきます。例えば、30代で建てた家を「終の棲家」と考えている方も多いかもしれません。注文住宅に限らず、家は建てたその瞬間がゴールではなく、住み続けてこそ真のスタートです。近年では一定の基準を満たした高性能住宅が主流となっており、適切に維持管理をすることで家の寿命も大きく延ばすことができます。子育てから老後までを見据えた家づくりは、将来の安心と快適さを実現するために重要なステップです。今回は、その中でも特に意識したいポイントをまとめました。
1. 木造住宅の寿命を意識する
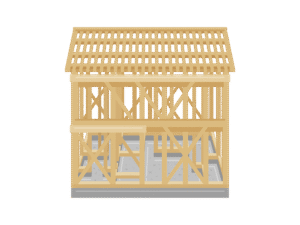
一般的に木造住宅の平均寿命は約30年と言われていますが、定期的なメンテナンスを行えば60〜80年も住み続けることが可能でした。ですが今後は新築するにあたり、一定の長期優良住宅の基準を満たすことが義務づけられており、住宅の寿命と価値を大きく高めることができます。その後の適切なメンテナンスにより、これからの住宅の寿命は100年を超えてくるでしょう。
2. 立地選びは老後も見据えて

買い物や通院の利便性は、子育て世帯や老後にもとても重要です。老後は車を運転できなくなった後の生活に大きな影響を与えるでしょう。徒歩や公共交通機関でアクセスしやすい場所を選ぶことが、将来的な安心に繋がります。
3. 回遊動線で生活しやすい間取りに

回遊性のある間取りは、家事効率を上げるだけでなく、将来の移動負担を減らします。特に、生活の中心を1階で完結できるように設計することは、老後に大きなメリットとなることでしょう。関連記事「注文住宅の間取りで後悔?経験者から学ぶ失敗談を5つ紹介。」も併せてご覧ください。
4. 水回りの配置はコンパクトに集約
キッチン、トイレ、浴室などの水回りを集約し、寝室やリビングからスムーズにアクセスできるようにすることで、移動の負担を減らせます。通路の幅やドアの仕様にも配慮しましょう。
5. 広めの玄関土間

玄関の土間は将来のバリアフリー化にも対応しやすく、車いすや歩行器を使う際も便利です。買い物や介助の準備スペースとしても活用できます。将来的に引戸にリフォームするととても楽になるでしょう。
6. 玄関アプローチ
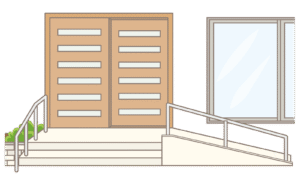
スロープの設置や段差の解消など、外部からの動線にも配慮しましょう。将来の移動のしやすさが格段に向上します。
7. 引戸の採用

開き戸よりも引戸の方が開閉がしやすく、車いすや歩行補助器を使用する場合にも適しています。握力が弱くなってくる老後は、引戸がとても便利になります。上吊り戸にすることでバリアフリーも叶い、何より掃除がしやすくなります。将来のリフォームを見越して、玄関や水回りに採用すると便利です。また玄関ドアの幅を広めにとっておくと、将来的にも安心です。
8. 廊下をなくす or 幅を広めに
廊下のない間取り、または幅を広めに設計することで、移動のしやすさや手すりの設置にも柔軟に対応できます。
9. ホームエレベーターのスペース確保
2階建て以上にする場合、将来的にエレベーターを設置できるスペースを確保しておくと安心です。生活の中心が1階にあっても、2階も活用できて便利になるでしょう。
10. 2階の使い道も考える
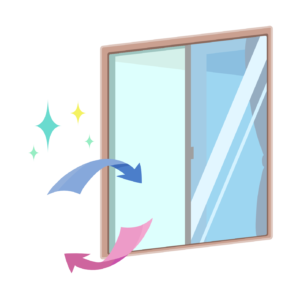
子供が巣立った後の2階は、物置として使われがちですが、定期的な掃除や換気を忘れず、空き部屋の有効活用を意識しましょう。2階を物置にしてしまうと物を積み重ねた状態となり、その結果風通しが悪くなり清掃が行き届かず、虫が湧いたりカビが生えることも。資産価値が低くなってしまいますので注意しましょう。
11. ライフステージに応じた設計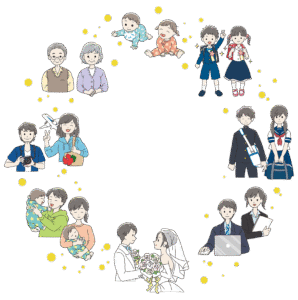
注文住宅を建てようと考える時、住まいの中で重視するポイントは20代、30代、40代と、ライフステージにより異なってきます。暮らし方は人それぞれ。将来の暮らし方を想像し、可変性の高い間取りを選ぶことが重要です。
12. 平屋という選択肢
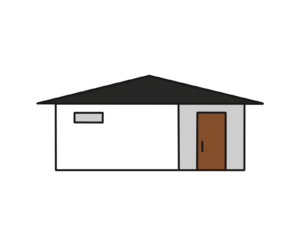 土地と初期投資に余裕があれば、平屋も有力な選択肢です。バリアフリー化がしやすく、構造も安定しているため、将来的なメンテナンス費用も抑えやすい傾向にあります。
土地と初期投資に余裕があれば、平屋も有力な選択肢です。バリアフリー化がしやすく、構造も安定しているため、将来的なメンテナンス費用も抑えやすい傾向にあります。
13.その他の細やかな工夫
□スイッチや棚の位置、コンセントの位置や数を将来的にも使えるように予め設計しておくと良いでしょう。
□家の中の寒暖差を減らす工夫をしましょう。現在は住宅の性能が上がっており、断熱性能も良くなっています。お風呂場などでも、従来よりも寒暖差は起こりにくいと言われていますが油断は禁物です。
まとめ
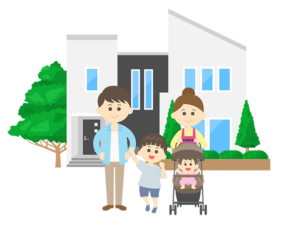
住まいは、家族の成長や老後の生活に合わせて変化させていくもの。今だけでなく未来を見据えた計画が、長く快適に暮らせる家づくりのカギとなります。注文住宅を検討している方はもちろん、リノベーションを考えている方も、これらの視点を取り入れて「未来も安心な家」を目指してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました!宜しければ関連記事「家選びが変わる?「省エネ住宅」がスタンダードになる未来とは。」もお読みいただけますと幸いです。